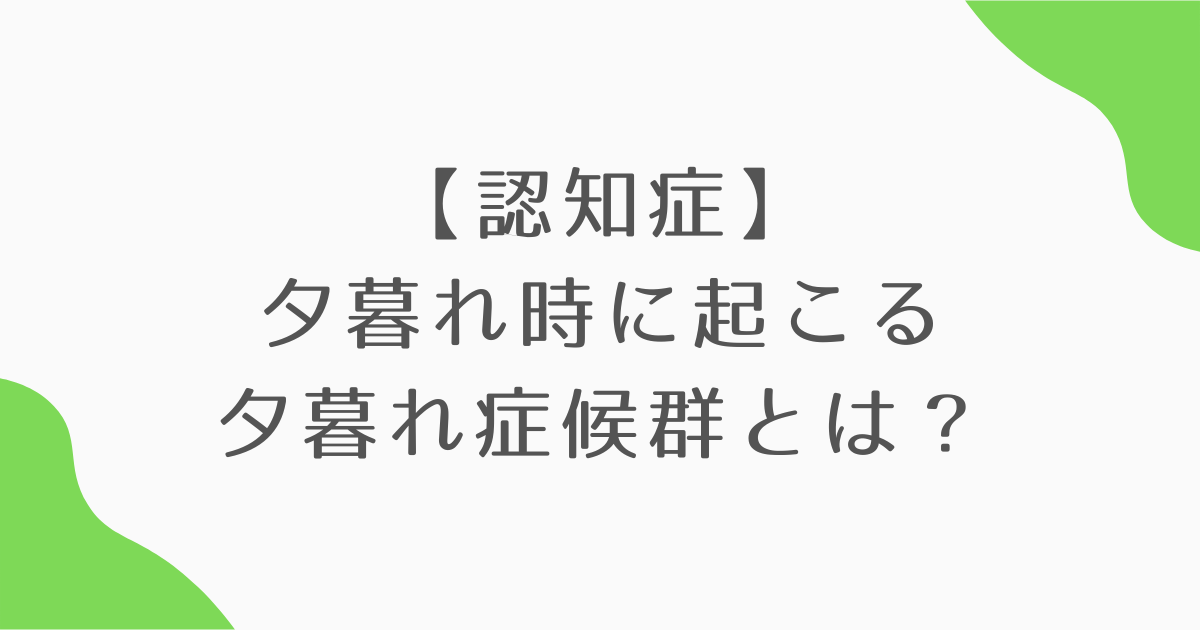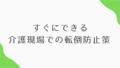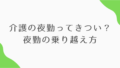認知症の方々が夕方になると落ち着かなくなる「夕暮れ症候群」。介護の現場で働く私たちにとって、この時間帯のソワソワとした行動は、日々の大きな課題の一つです。夕方になると、なぜか落ち着かなくなる利用者の方々。その理由について、一緒に考えてみませんか?
私の勤める施設では、夕方は掃除の時間。でも、送迎で職員が不在になると、ちょうどその時に限って、利用者の方々が落ち着かなくなるんです。そんな時、業務はなかなか進まないですよね。
夕暮れ症候群の原因は?
夕暮れ症候群の原因はまだ完全には解明されていませんが、いくつかの考えられる要因があります。
体内時計の変化
認知症になると、体内時計が狂いがち。日が暮れると「もう夜だ」と感じてしまい、不安や混乱を招くことがあります。
感覚の低下
視力や聴力の衰えも一因。薄暗くなると、周りが見えにくくなり、不安を感じやすくなるんです。
疲労
一日の疲れがピークに達する夕方。脳の活動が低下し、不安や混乱が生じることも。
みなさんも疲れた時イライラしたりしませか?
過去の記憶
認知症になると、過去の記憶と現在が混同しやすくなります。特に、夕方になると日中の出来事を忘れ、過去の記憶が蘇り帰宅願望などの症状が出ます。
例えば、かつて夕方に帰宅していた記憶が蘇り、施設にいるにもかかわらず職場にいると勘違いし、帰宅しようと徘徊してしまうことがあります。
薬の影響
服用している薬によっては、夕方になると副作用が現れることがあります。
夕暮れ症候群の症状にはどんなものがある?
夕暮れ症候群の症状は人それぞれですが、よく見られるのはこんな感じです。
不安や焦燥感
「家に帰りたい」「もう遅いから帰ろう」などと言って、落ち着かない様子を見せる。
混乱
時間や場所が分からなくなり、徘徊したり、意味不明なことを言ったりする。
興奮
怒鳴ったり、暴れたりすることがある。
うつ状態
悲しそうにしたり、何もやる気がなくなったりする。
夕暮れ症候群への対応方法は?
完璧な対応方法はありませんが、こんな対応方法が考えられます。
規則正しい生活を送る
体内時計を整えるためにも、毎朝同じ時間に起きて、しっかり日光を浴びることが大切。
曇っていてもカーテンを開け光を浴びましょう!
日中に適度な運動をする
日中に適度な運動をすることで、夜間の興奮や不安を抑制することができます。レクリエーションや散歩などを通して適度に運動する機会を提供しましょう!
でも疲れすぎには注意。適度に休養の時間を!
夕方にはリラックスできる環境を作る
照明を落としたり、音楽を流したりして、心地よい空間を。
不安な気持ちに寄り添う
不安そうな様子があれば、優しく声をかけ、話を聞いてあげましょう。なにかに困っていて、答えが見つからなくても一緒に原因や解決策を考えてあげると孤独感を和らぐかも。
必要に応じて薬の調整を行う
服用している薬の副作用が原因の場合は、医師に相談して薬の調整が必要です。
まとめ
夕暮れ症候群は、認知症が引き起こす症状の一つです。原因や症状、対応法を理解した上で利用者の状態を観察するとその人なりの解決方法が見つかるかもしれませんね!