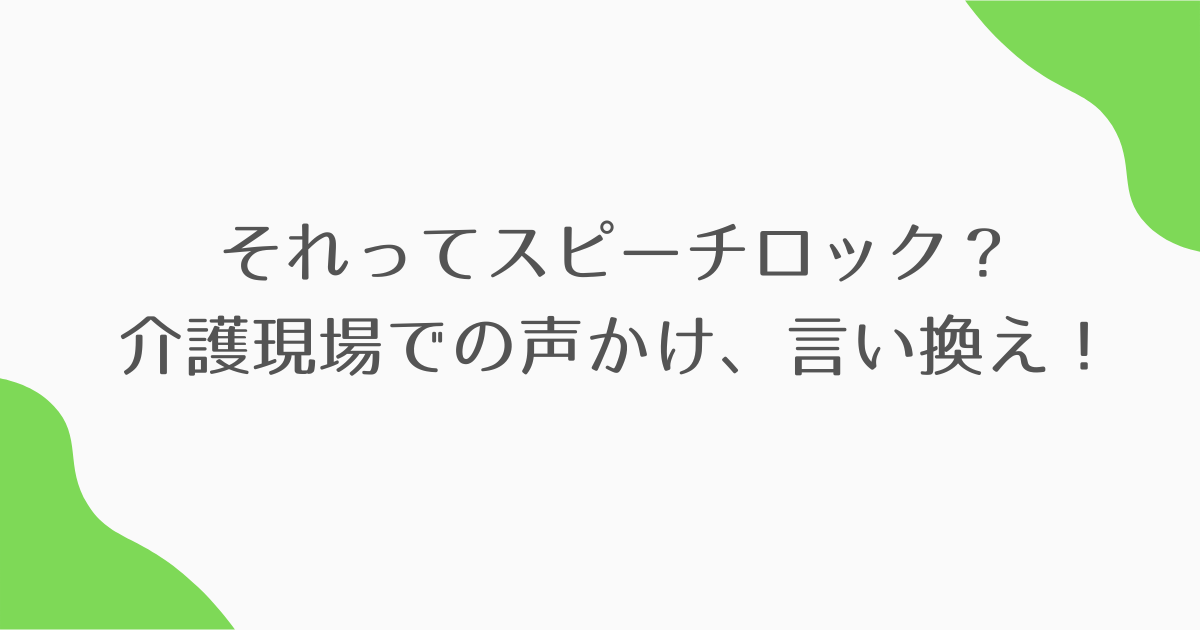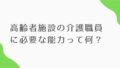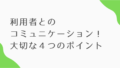介護現場で例えば、こんな場面
忙しい現場!
オムツ交換中!
多量の便!
汚さないように注意しながらオムツを交換していると部屋に入ってきて
「私の服がないんだけど」と利用者さん。
(手が離せないし、オムツ交換中だからそもそも入ってこないで!)
「ちょっと待っててください」
つい言っちゃいますよね!
でも実は、その言葉がスピーチロックに繋がるかもしれません。
少し耳が痛い話かもしれませんが、ここでは、つい言っているかもしれないスピーチロックについて解説していきます。
スピーチロックとは
言葉で相手の行動を制限してしまうことです。
身体拘束には3つのロックがあります。
フィジカルロック
ドラッグロック
スピーチロック
フィジカルロックとはベルトやベッド柵などを使って物理的に相手の行動を制限すること。
ドラッグロックとは夜間徘徊する人や声をあげてしまう人などの状態を抑えるために
安定剤や眠剤を使用して行動を制限すること。
この2点は道具や薬が必要なのでそれをなくしてしまえば
防げますが、スピーチロックはなにもなくても言葉だけで、できてしまうので
防ぐことが難しいと言えるでしょう。
なぜスピーチロックは起こる?
起こる原因として以下のようなことが考えられます。
業務に追われて忙しく余裕がない
利用者の安全のため
利用者の視点からの意識が欠けている
これらの原因が絡み合って起こる原因になっていると考えられます。
スピーチロックがダメな理由
信頼関係を損ねる
言葉によって行動を制限してしまうと、コミュニケーションがとれなくなり
信頼関係を損なっていまい介護拒否などに繋がるかもしれません。
認知症の悪化
認知症の方は言われたことは忘れても、その時の感情は強く残る場合があります。
それにより症状が悪化したり、介護拒否につながることも。
行動意欲やADLの低下
言葉によって制限をかけられると、利用者さんの意思決定や行動が減ってしまい
ADL(日常生活動作)の低下につながることも。
私たちも上司にやることなすこと全て否定され怒られたらやる気がなくなりますよね!
スピーチロックの防止策
スピーチロックへの理解
研修や会議などを行い、スピーチロックへの理解を深める機会を作りましょう!
業務の忙しさでそれが悪影響だということを忘れてしまっていることがあります。
理解を深めて、再確認することでスピーチロックを防止できる環境を作ることが大切です。
利用者の立場になって考える
自分が将来介護が必要になった時にその言葉を言われてどう思うかを考えましょう!
嫌じゃないですか?
言い換えの言葉を考える
言い換えの言葉を考えておき忙しい業務中でもとっさに使えるようにしておきましょう!
いくつか例文を載せておきます。
・ちょっと待って! → ○分後に行きますので待っててくれますか?
・座ってて! → 立ち上がると危ないので座ってていただけますか?
・〇〇して! → 〇〇したいので、〇〇していただけますか?
・〇〇しないで! → 〇〇なので、〇〇しないでいただけますか?
・動かないで! → 一緒に行くので、待っててもらえますか?・
・早くして! → あわてないで、ゆっくりでいいですよ。
・なんでそんなことするの? → 〇〇なので〇〇のようにしませんか?(説明して置き換える)
・忘れないでください!→ 何度も根気よく説明する。
命令口調や否定形ではなく依頼形で言い換えましょう。
話す時は笑顔で声かけをすることも忘れずに!
余裕を持つ
自分がイライラしていては相手に穏やかに話すこはできませんよね。
まずは自分を整えましょう!働きやすい職場環境を作ることも重要です。
まとめ
スピーチロックは言葉だけでできてしまうだけに、起こりやすく
簡単に利用者さんへ悪影響を与えてしまうので、防ぎたいところですね。
ただ僕らも感情を持っている人間なので、時にはイラッとすることもあると思います。
100%なくすことは無理でもなるべく減らせていけれればいいのかな
と僕的には思いますので、一緒にがんばりましょう!